教員紹介
-
 新井 信幸ARAI Nobuyukiコミュニティデザイン研究室
新井 信幸ARAI Nobuyukiコミュニティデザイン研究室現代の建築の計画・設計では、ハード・ソフト両面を検討することが重要となっており、図面や模型の製作だけでなく、社会状況、地球環境への配慮、新たな価値の創造等、時代を展望できる広い視野が求められています。
-
 有川 智ARIKAWA Satoshi建築マネジメント研究室
有川 智ARIKAWA Satoshi建築マネジメント研究室建築を取り巻く社会的・経済的状況を踏まえながら、「いいもの」とは何かを考え、「きちんと手入れして」いくための技術やしくみを検討し、「長く大切に使う」ことの意義を一緒に追求していきましょう。
-
 石井 敏ISHII Satoshi福祉住環境デザイン研究室
石井 敏ISHII Satoshi福祉住環境デザイン研究室豊かで安心して暮らせる社会とそれを支える環境の創造。建築が関わる領域はとても広く深い。目の前に広がる現実の理解と、そこに生きる人に対しての温かい眼差し。それが未来の暮らし、社会をつくります。
-
 鍵屋 浩司KAGIYA Koji環境・防災システム研究室
鍵屋 浩司KAGIYA Koji環境・防災システム研究室建築やまちづくりの立場から日常の生活を安心で豊かなものにする方法を自由な発想と技術的な可能性で裏付けて「かたち」にして社会に向けて提案していきます。
-
 菊田 貴恒KIKUTA Takatsune建築材料工学研究室
菊田 貴恒KIKUTA Takatsune建築材料工学研究室環境に対する負荷をどのように低減するのか?と言う社会的な大きな流れの中、建築物に求められる性能は高度化・複雑化してきています。これからの50年、100年先の建築を一緒に探求していきましょう。
-
 許 雷XU LeiBIM研究室
許 雷XU LeiBIM研究室CADツールは単純な製図道具として見過ごされてきましたが、建物情報モデリング技術を加え、CADツールは考えてくれる「匠の手」に進化していきます。「感」で環境のことが分かりますが、一緒にやってみませんか?
-
 薛 松濤XUE Songtao構造工学研究室
薛 松濤XUE Songtao構造工学研究室建物の振動変化について調べ、そして、建物の状態を把握する研究及び仕事を行なっています。変化(動)があっても頑張って乗り越えるような学生が適切です。
-
 中村 琢巳NAKAMURA Takumi建築史研究室
中村 琢巳NAKAMURA Takumi建築史研究室匠の手仕事、和のデザイン、エコロジーといった様々な視点から、木材などの自然素材による伝統建築の魅力が見直されています。歴史をひも解く文系的な理論分野ですが、建築史の学びは様々な場面で応用へもひろがります。
-
 福屋 粧子FUKUYA Shoko建築デザイン研究室
福屋 粧子FUKUYA Shoko建築デザイン研究室「絵や映像だけで話すように表現する人」「街がこんな風であったらいいと思ってる人」「出会った風景の面白さについて何時間でも語りたい人」いろいろな「変」人が出会い、自分の個性を伸ばしていく分野だと思います。
-
 船木 尚己FUNAKI Naoki地震減災・防災研究室
船木 尚己FUNAKI Naoki地震減災・防災研究室地震国である日本で建物をつくるということは、単に雨露を凌ぐだけでなく、大地震から人々の生活を守る建物をつくることを意味します。それは人の命に直結しています。そういったことを常に意識して勉強できる人が構造の分野では向いていると思います。
-
 堀 則男HORI Norio損傷制御システム研究室
堀 則男HORI Norio損傷制御システム研究室地震の力は直接建物を押しているわけではないので,これに対抗して揺れを抑える方法も,直接建物を止めるような方法は採れません。地震から多くを学んでいる東北の地で,地震被害を抑える工夫を考えてみませんか。
-
 大石 洋之OOISHI Hiroshi建築環境学研究室
大石 洋之OOISHI Hiroshi建築環境学研究室建築環境学分野では快適な建築空間に必要な熱・空気・音・光環境の基礎理論を学びますが、これらは今後ゼロエネルギー建物を目指すうえで必須の知識となります。また、これからは建築を取り巻くエネルギー問題や地球環境に関する幅広い視野が必要です。
-
 齋藤 隆太郎SAITO Ryuutarou建築デザイン、建築計画研究室
齋藤 隆太郎SAITO Ryuutarou建築デザイン、建築計画研究室建築は総合学問であり、かつ社会的及び芸術的側面に実を成す、非常に多角的な視点からアプローチが可能な実学です。建築を通じて社会に対する責任を意識することが、建築という分野を楽しむ初歩となります。
-
 曹 淼Miao Cao知能建築研究室
曹 淼Miao Cao知能建築研究室100年近く前に,耐震設計の考え方を巡って,「柔剛論争」と呼ばれる論争が繰り広げられました。後々,現在日本の構造設計の礎となったのです。柔と剛一見真逆のことに見えるが,時代が激しく変化している中,社会の多様性に適した技術者に一番欠かせない資質とも言えるだろう。
-
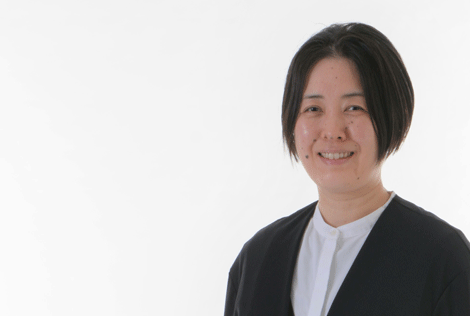 錦織 真也NISHIKORI Maya建築・インテリアデザイン研究室
錦織 真也NISHIKORI Maya建築・インテリアデザイン研究室自分が経験してきたこと、身の回りのあらゆることが学びとなるところに、建築の学問としての懐の深さ・魅力を感じています。学生のみなさんとも私自身が感じている建築のおもしろさややりがいを共有することができればと思います。
-
 不破 正仁FUWA Masahito地域計画研究室
不破 正仁FUWA Masahito地域計画研究室まちを歩き、記録を取ること、この二つがまちづくりにとっての重要な要素を導き出すきっかけとなります。身近なまちにはどんな魅力があるでしょうか?そして、どんな課題があるでしょうか?まちづくりは、この疑問を持つことから始まります。
-
 畑中 友HATANAKA Tomoyuki構造性能維持システム研究室
畑中 友HATANAKA Tomoyuki構造性能維持システム研究室地震などの災害で被害を減らすためには、災害発生時だけでなく発生後の建物の安全性や機能維持が大切です。実験や解析、防災教育を通じて災害後も安全で安心して使うことのできる建物を目指し、様々な課題に一緒に取り組んでみませんか。
-
 笹本 剛SASAMOTO Takeshi
笹本 剛SASAMOTO Takeshi現在、人々の生活が大きく変化し、それに伴い住宅に対する要求も多様化してきています。このような状況の中で、様々な生活と住宅の関係を読み解くことによって、現在の住宅の姿を把握し、今後のより良い住宅の姿を考える研究を行っています。














